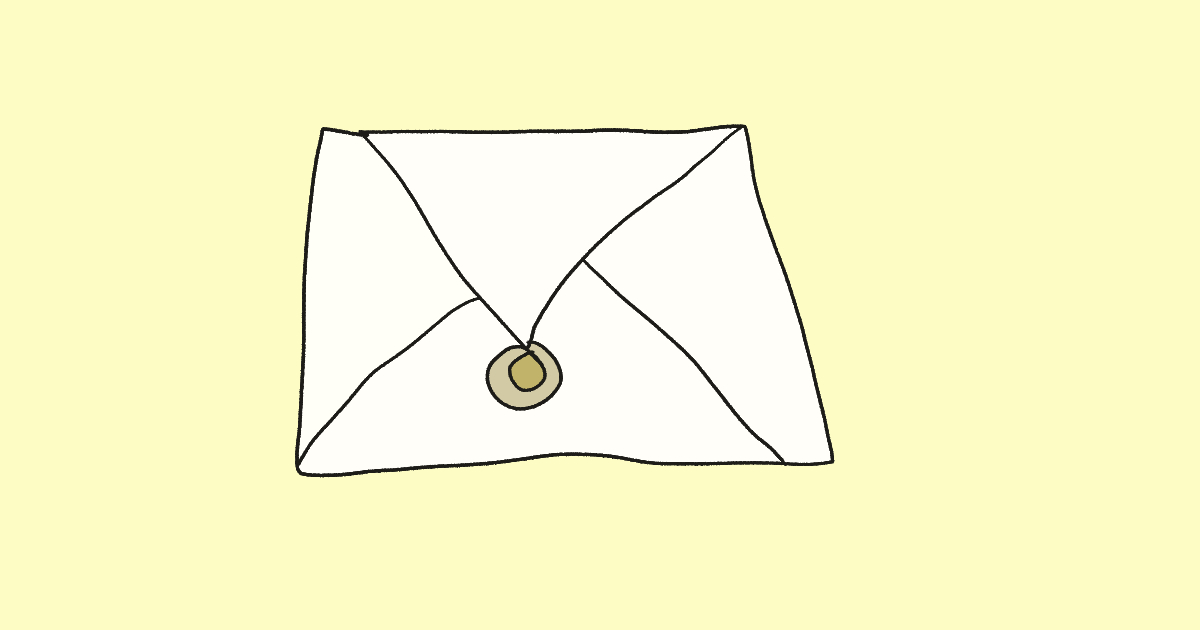3分で読める自作ショートショートです。通勤時間などすき間にサクッと読めちゃう、不思議系超短編ストーリー。
今回のテーマは、「干からびた休日を過ごしている女性が”差出人不明の手紙”を見つけることから始まる」という話です。何故、差出人不明の手紙がポストに入っていたのか?その真相にきっとあなたも度肝を抜かすでしょう……。
差出人不明の手紙
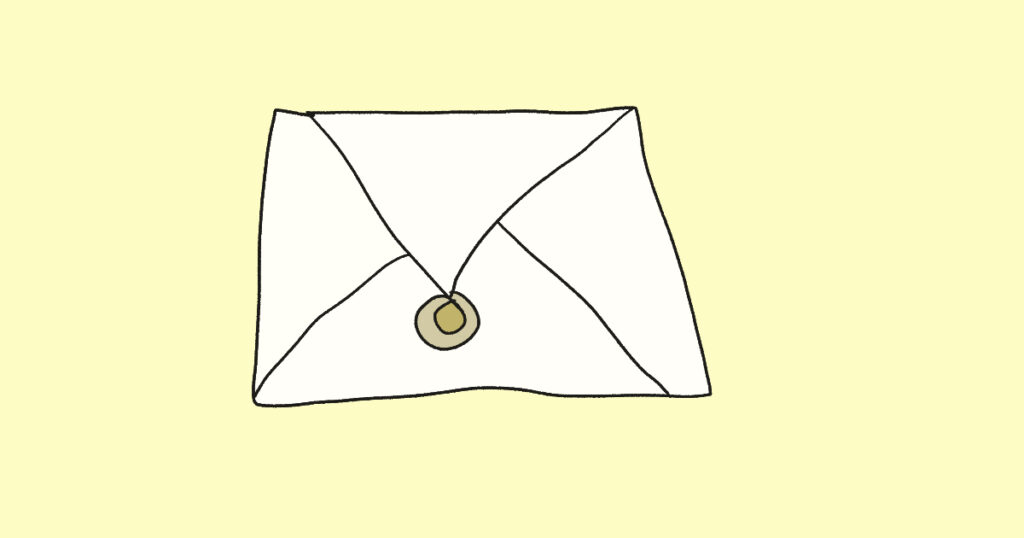
ある日郵便受けを見たら、一通の厚みのない薄っぺらな封筒が入っていた。
私は都内の中小の事務をしている。24歳の干からびた女性である。
何故干からびたと言えるかと云うとプライベートでは高校の時の赤いジャージを着て、昼間からビールにスルメイカを食べる休日を過ごしているからだった。
勿論、休日は、メイクもしないでダラダラとビール片手にスマホをポチポチしていた。
今はというと、夕方になったので郵便受けが溜まっていないかと見に外にちょっこと出てみた。
そうしたら、手紙らしき郵便物があった。
封筒の中身を見ると一枚の便箋が入っていた。
『拝啓 大村有里様 元気でお過ごしでしょうか?
僕は貴女を一目見て好きになりました。
けれども、もう会えなくなるのが寂しいです。』
(なにこれ?)
ていうか、誰からの手紙が良く分からなかった。
(これどういう風に返したらいいの?)
続き:差出人不明で手掛かりなし
私は早速手紙を出した人物を特定するためにスマホの連絡帳を開いた。
「男の連絡先って何人かな?」
「あ、1人居てた。あれ?もう1人いる」
結果、3人の男と連絡先交換していたみたいだった。
「でも内、2人は既婚者のおじ様だな。これはこいつしかいないことになる」
その男の名前は、関内阿月だった。
この男は、20代後半だった気がする。関内は、見るからに草食系の男子?だった気がする。いつも本読んでたし、っていうかさっきから、うる覚え過ぎて申し訳なくなってきた。
「どうしていいか分からないけど、とりあえずそれとなく聞いてみるか」
関内に電話を掛けてみた。
「はい、もしもし関内です。大村さん、どうかしましたか?」
「あ、あのね。手紙出した覚えってない?」
「手紙?なんですか?それ?」
「あーそう。分かったわ。急に電話かけてごめんね」
「あ、いえ」
関内が普通に知らなかったようなので、電話を切った。
私は内心手紙の主が関内ではなかったことに動揺した。
「え、誰?怖くない?」
私の中で一気に迷宮入りした。
「この手紙のことは忘れよう」
そう言い切って、私はこのことから距離を置くことにした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
一週間後
会社に行くと新しく人が入って来た。
「中途採用の森内昴です。よろしくお願いします」
森内は元々ベンチャー企業で働いていたが、社長と意見が合わず辞めることになったらしい。
(ここの会社って噂話すぐに回るよねー。生きづらい面だわ)
昼休み、私は一人で社食を食べていた。
「大村さん、ご一緒してもいいですか?」
「え、あ、いいよ」
森内は、体が大きくガタイがいいのだが、少し、童顔よりな顔をしていた。
「近くで見ると少し可愛らしい顔だねー」
「え、あ、はい。もう28歳なんですけどね。よく言われます」
「え、28歳!ごめんなさい。年上の方にそんなこと言って」
森内は苦笑いをしたように見えた。
その後、森内と私は昼休みの時会話をするようになった。
続き:手紙のことを話したら
「恋文ですか?それ?」
森内は目を丸くさせて言った。
「そんなに大したことでもないよ。だって、誰がくれたか分からないから」
「え、そうなんですか!」
森内は、驚きつつも何か思い出したかの様に口を開いた。
「俺、小学生の時に引っ越しの前に手紙で気持ちを書いて、告白したことがありました」
「でも、自分の名前書くのを忘れてた気がする」
森内は、誰に書いたかを思い出そうとしていた。
「まさか、大村有里宛に書いた?」
思わず口を挟んでしまった。
ドキドキと胸が締め付けられそうになった。
「あ、そうそう、同級生の子で大村有里さんに宛てた手紙です」
「え、ど、同級生?」
「違うかー、同姓同名の人だったのかな?」
「そうかもしれませんね。今手紙あります?」
「あ、どうだろう?」
私はカバンを見てみた。
「あ、あった。ほらみて」
森内は、手紙を読むと
「あ、これ俺の書いた手紙です。間違えて送られてますね」
森内のあっさりとした言い方に鳥肌が立った……。
お終い
※この物語はフィクションです。